どうも。TrioFです。
今年初めから異動になって、全く新しい分野に飛び込むことになりましたが、1月以上経って、早速PMの業務をアサインされ始めています(汗)
とはいえ、入社以来、ほとんどプロジェクトマネジメント(PM)的な業務に携わったことがなく、それにも関わらず、それなりに大きなチームを受け持つことになりそうで、戦々恐々としています💦
いくら知識を詰め込んでみても、こればっかりは経験するしか道はないと思います。ただ、やっぱり基本的な考え方がベースにないと、取り組み方が行き当たりばったりになり皆さんに迷惑を掛けてしまうと思い、本屋を巡ってみました。
そこで出会った良書が、中嶋秀隆氏著「プロジェクトマネジメント」でした。
| PMプロジェクトマネジメント[本/雑誌] / 中嶋秀隆/著 価格:2,750円(税込、送料別) (2025/2/16時点) 楽天で購入 |
PMの内容が初心者にも分かりやすいように体系的にまとめられてあり、個人的にはイラストも見やすくて、頭にスッと入ってくる本でした。
また、「Column」と題して、PMの実情のようなものを豊富に語って下さり、理解を深めるのにとても役立ちます。
具体的な事例も挙げつつ説明が展開されるので、イメージが湧きやすいのも良い点です。
以下に、自分への備忘録も兼ねて、内容の大項目を列記してみます。
プロジェクトの発足を通知する
ここでは、プロジェクト発足のトリガとなるアクションが整理されています。確かにこういったキチンとしたアクションがなく、何となくプロジェクトが始まってしまうことってありますよね(汗)重要なステップだと思いました。
- ビジネス・ニーズを検討する
- プロジェクトの妥当性を判断する
- プロジェクト・マネージャーを任命する
- プロジェクト憲章を発行する
背景を確認し、プロジェクト目標を設定する
目標設定を的確に行うことは当然欠かせません。ただ、実際の現場ではなおざりになりがちです。。。この章では「プロジェクト目標を設定するには?」という観点で重要なアクションが整理されています。
特に「QCDの優先順位を決める」は大切ですよね。
- プロジェクト・チームのキックオフをする
- ステークホルダーのニーズを検討する
- 成果物とスコープを決める
- QCDの優先順位を決める
- 「プロジェクト目標」を文書化する
- 変更管理の手順を決める
- プロジェクトの基本ルールを決める
- 「プロジェクト・ファイル」にまとめる
ワーク・パッケージを洗い出す
個人的には、この章の内容が一番今の自分に求められるポイントの1つなのかな、と思いました。WBSとは、Work Breakdown Structure(作業分解図)の略ですが、このアクションをどこまで適切に行えるかが、とても大切だと思います。
- WBSを作る
- 作業をどこまで分解するか?
- 作業記述書
ワークパッケージを「〇〇を✕✕する」とキチンと書き表せているか。〇〇が成果物であり、✕✕が作業が完了したかの判断基準。
う〜ん。↑とっても重要なアクションですね。。。「40時間の原則」というところも、改めて得た視点で、頭に叩き込んでおこうと思います。
役割を分担し、所要時間を見積もる
言わずもがなですが、このステップもとっても重要ですね!ここの部分がいつもなおざりになっているような気がします(自分たちの会社だけかもしれませんが)。PMの肝となるアクションですね。。。
- 役割を分担する
- 所要期間を見積もる
- 作業工数と所要期間
- 時間見積もりの進め方
- 可変時間作業と固定時間作業
- 時間見積もりのモデル
- 作業工数の見積もり
- 所要期間の見積もり
- 所要期間見積もりのステップ
- WBSと所要期間見積もり
バランスのとれたスケジュールを作る
お客さんからの、スケジュールに対するプレッシャーにはいつも悩まされます。納期遵守は大切なので、適切に対処したいですよね。。。
クリティカル・パスもですが、フロートの有効活用も重要になってきます。注意深くスケジューリングすべきですよね。
- ネットワーク図を作り、クリティカル・パスを明らかにする
- ネットワーク図を作る:右脳アプローチ
- ネットワーク図を作る:左脳アプローチ
- 依存関係の誤り
- ループ
- ハンガー(宙ぶらりん)
- 重複
- クリティカル・パスとは何か?
- クリティカル・パスの往路分析と復路分析
- 往路分析:最早開始・最早終了を求める
- 復路分析:最遅終了・最遅開始を求める
- フロートを求め、クリティカル・パスを明らかにする
- クリティカル・パス分析の意義
- スケジュールを図示する
- ガント・チャートを作る
- 依存関係のいろいろ
- リードとラグ
- クリティカル・パスを短縮する方法
- マイルストーン
メンバーの負荷をならす
いつも個人的に気になるのはメンバーの負荷です。今はコンプライアンスも厳しくなっていますし、特に特定の人だけに負荷がかかって属人的になるような状況は避けたいです。
生身の人間と共に仕事をしているんだ、という気持ちを忘れず取り組みたいです。
- メンバーの負荷を把握する
- メンバーの担当をガント・チャートに書き込む
- メンバーの負荷の自己申告をガント・チャートに書き込む
- メンバーの負荷を算出してガント・チャートに書き込む
- 負荷を図示する
- 負荷をならす方法
- 負荷の調整をスケジュールに反映させる
予算・その他の計画を作る
予算を強く意識した検討はいつも課題となります。結局、プロジェクトとして適切な利益が享受できなければ本末転倒であり、ビジネスとして何の意味も成さなくなりますもんね。。。
- 予算の作成と管理
- 費目を決める
- 人件費を求める
- 経費を見積もる
- 予算表、予算グラフを作る
- アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)
- 品質計画を作る
- ステークホルダー計画を作る
- コミュニケーション計画を作る
- 資源計画を作る
- プロジェクト・チームを育成する
- 物的資源を投入する
- 調達計画を作る
リスクに備える
リスクマネジメントも、とても大切ですね。ポイントは、リスクを適切に分析して評価することだと思います。
リスクは挙げ始めればいくらでも出てきますし、対処コストも鑑みつつ検討しなければなりません。PMの肝になるアクションですよね。。。
特に最近はセキュリティのリスク対策が重要になっており、充分な検討が欠かせません。
- リスク分析の方法
- リスクを洗い出す
- リスクを絞り込む
- 予防対策、発生時対策、トリガー・ポイントを決める
- リスクに備える
- 健全な危機感とリスク分析
- リスクを考えることは健全
- リスク・マネジメントの原則
- 想定外の事態には迂回策で対処
承認を取りつけ、ベースラインを設定する
自分の場合は、幹部への承認作業が1つの具体的なタスクとして挙げられますが、キチンと整理して臨みたいですね。
これも実際にはなかなか大変な作業なのですが、承認を取るために上手く見せようといった作業でなく、事実に基づいて適切に対応したいところです。。。
- 計画段階のまとめ
- 計画チェックリスト
- 承認、基準計画、プロジェクト・ファイル
- 承認を取りつける
- 「基準計画」を発足させる
- プロジェクト・ファイルにまとめる
作業を実行し、変更をコントロールする
プロジェクトが走り始めると、色んなことが起こると思いますが、チーム内の風通しを良くして対応したいですね。
レビューの為のレビューにならないよう、課題があれば腹を割って協議できるように努めたいです。
- 作業を実行する
- 実績データを集める
- 実績と計画を比べる
- 差異の原因を究明し、影響を分析する
- 是正措置を講じる
- プロジェクトの計画を変更する
- 現状と変更点を報告する
- 報告書を提出する
- レビュー会議を開く
- レビュー会議の前に
- レビュー会議の場で
- レビュー会議のあとに
- プロジェクトのスコープをコントロールする
- スコープの変更の原因
- スコープの変更をコントロールする
プロジェクトを終え、教訓を得る
多数のプロジェクトが走っている状況だと、こういった振り返り作業はどうしてもなおざりになりがちですが、とっても重要ですよね。記憶が薄れない内に、あまり時間をおかず後回しにせずにアクションすべきだと思います。
こういった活動がアセットとして積み上がり、競争力にも繋がっていくのだと思います。
- 事後の振り返りの進め方
- 最終の実績データを集める
- 事後の振り返り会議を開く
- 文書にまとめ、記録を残す
- 事後の振り返り会議で取りあげるポイント
- 終了を祝い、労をねぎらう
さいごに
「PMについて何か良い本ないかな」とフラッと本屋に立ち寄った感じではあったのですが、幸運にも、とっても分かり易い良書に出会えて嬉しかったです。ラッキーでした。
あとはどれだけ実践できるか?だと思うので、日頃の業務で意識して取り組んで、自分の血肉にしていきたいです。
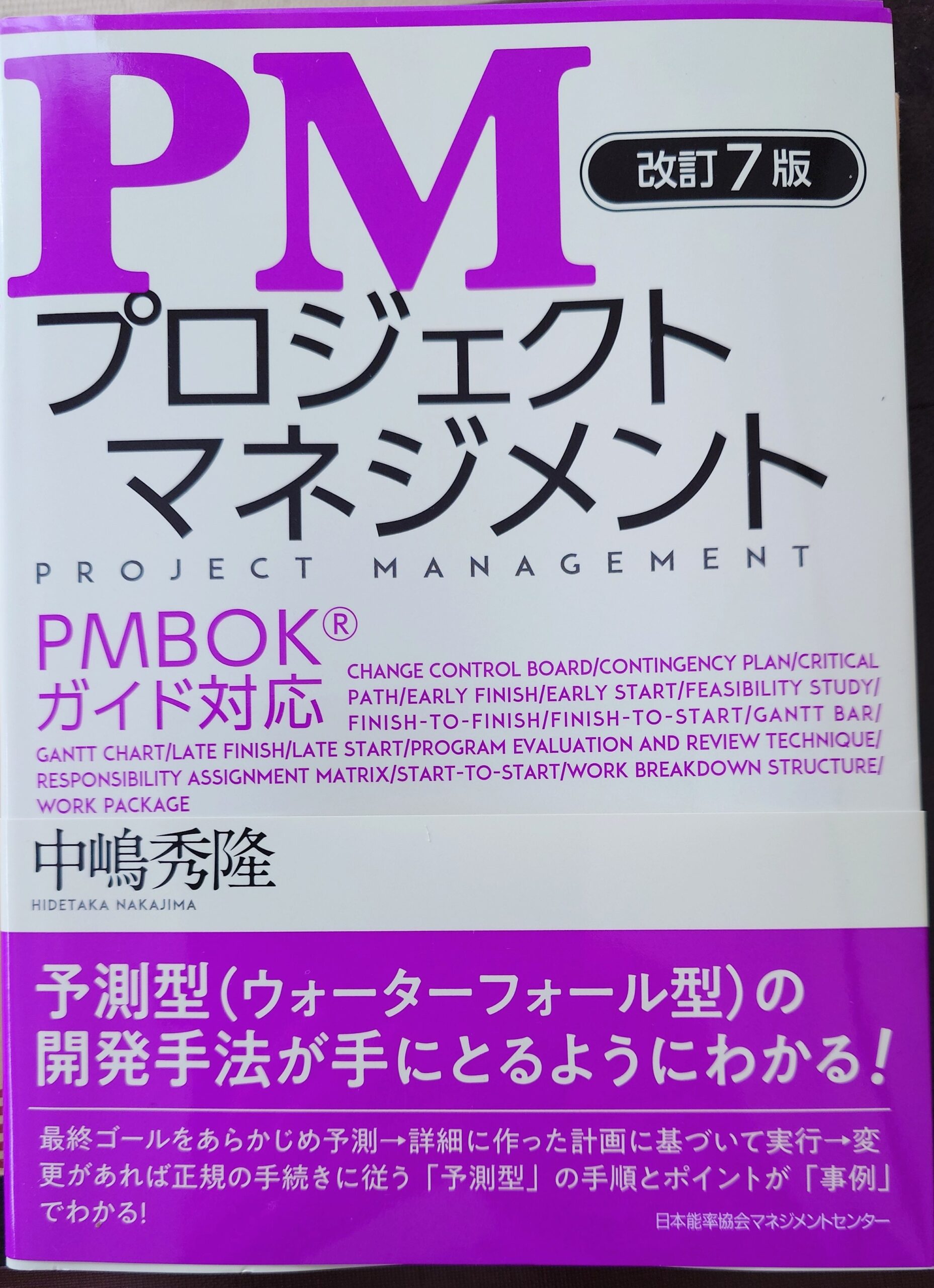


コメント